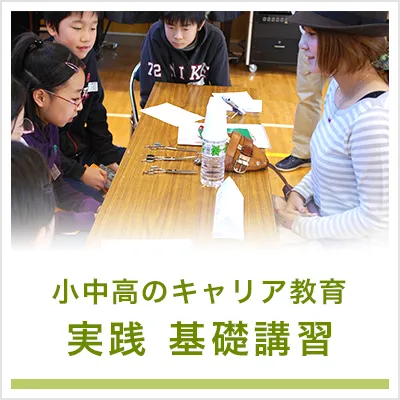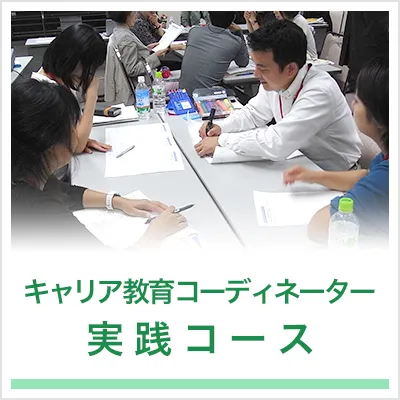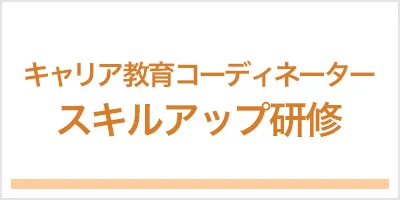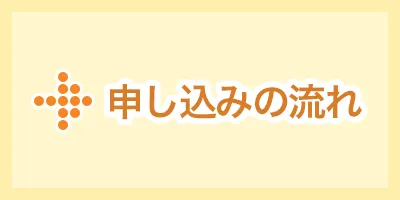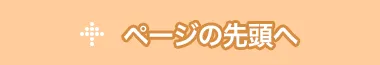受講者インタビュー
学校と社会の繋ぎ役をめざして
宮田 樹弥さん(2023年度受講)
もっと深く教育に関わることがしたい
大学進学時には教師を目指しており、在学中には教員免許も取得しました。就職活動の際は、自分の好きな“旅行”と“教育”をどちらもできる教育旅行の分野に魅力を感じ、旅行会社に進みました。ただ、実際に働く中で、当初思っていたほど教育に関わっている実感が持てず、次第に物足りなさを感じるように。「教育にもっと深く関わることがしたい」と考え、転職も視野に入れて情報を集めていた時、キャリア教育コーディネーターの存在を知りました。「これなら自分自身がもっと教育に関われるのでは!?」と思い、その仕事の実態や関わり方を知りたくて受講を決めました。
実践コースでの「授業をつくりあげている実感」
都内にある女子校の授業の枠をいただき、ゲスト講師を招いて自分のターニングポイントについて語ってもらう授業を実施しました。ゲスト講師の選定および連絡、学校との打ち合わせ、授業内容(ワークシート)の作成、タイムスケジュールの調整などやることは本当にたくさんあり色んなことを同時並行で進める必要がありました。毎週のようにチームメンバーと打ち合わせをしていて、感覚的には“仕事”でしたね(笑) その分、授業を作り上げている実感はとてもありました。また、自分だけでは気づかないことをチームメンバーからたくさん学ばせてもらいました。
具体的に伝えることの重要性を学ぶ
日中は普通に仕事も行いながら、実践コースの準備も進めるので大変でした。しかし、キャリア教育コーディネーターがどんな仕事をしているのか知りたいと思って受講したので、その目的はしっかりと果たせましたし、受講して良かったと思っています。特に大変だったのは、チームメンバーとの認識合わせでした。各ゲスト講師との連絡はチームメンバーそれぞれで行っていたので、まさに伝言ゲーム。メンバー同士の認識がずれたまま伝えてしまい、出てきたアウトプットが「なんかちょっと違うかも」というようなこともありました。これはメンバー内だけでなく、先生に対しても同じことで、誰が見ても同じように理解できるように、具体的に伝えることの重要性を学びました。
関わりたいと考える大人はたくさんいる
現状はあまり活動できていませんが、児童・生徒の選択肢を広げる活動に携われたら良いなと思っています。私自身、いわゆる“普通の”学生生活を送ってきましたが、大人になった今振り返ってみると「あの時にこういう話を聞けていたら…」、「こういう体験ができていたら…」と思うことがたくさんあります。一方、社会にはそういうことを伝えたいと思っている人や会社もたくさんあることが分かりました。だからこそ、学校と社会の繋ぎ役として関わるキャリア教育コーディネーターの特性を活かし、一人でも多くの児童・生徒が「あの時にこういう話を聞いたから」と考えてキャリア選択を行えるようなお手伝いをしていきたいなと思います。とはいえ、すぐに何かができるわけではないので、まずは情報収集や人脈構築から進めたいと考えています。
これから学ぶ方へ
大変なこともありますが、とても充実した学びを得ることができると思います!楽しんでください!この講座を受講することもあなたの選択肢を広げることの一つです。
(2025年6月)
“誰か”ではなく“自分”の意思で選べる力を育てたい
大平 遥菜さん(2023年度受講)
小中高大学生の支援を
キャリアコンサルタントの資格を取得後、これから誰に対して支援をしていきたいか考えていたとき、小中高大学生向けがいいなと漠然と考えていて、キャリア教育という言葉に出会いました。その時、これをやりたい!と強く感じたことを今でも覚えています。私は、自分の進路やキャリアについて、自分で意思決定してきたもののどこかで「誰か」を気にしながら、意思決定してきました。そのため、「自ら」生きる力を発見していくキャリア教育を学ぶことは、私にとって、とても魅力的で受講することに迷いはありませんでした。
仕事以外の多くの時間は実践コースに・・・
私たちは、実際の高校の授業の機会をいただきました。私たちはその中でゲスト講師のコンテンツを作成しました。ゲスト講師が登壇する当日の授業だけでなく、事前・事後の授業の枠もいただき、そのために、学校の先生へのヒアリング、授業づくりのためのチームでのミーティング、ゲスト講師との打ち合わせ、教材の作成と授業後のアンケート作りをしました。チームでのミーティングについては、ほとんど週1回のペース、それ以外にも教材やアンケート作成等の資料作りなど、振り返って思うと仕事以外の多くの時間を実践コースの活動に充てていたと思います。
授業づくりはほんとうに大変
まず、ひと言でいうと、「受講してよかった」です。授業づくりの大変さを身をもって実感することができました。また、チームメンバー及び学校の先生との共通認識を持つことの大変さと難しさを感じることができました。私たちは、6名チームで、年齢はもちろんのことバックグラウンドも様々、言葉のニュアンスなどの違いから、ある時は、異なるアウトプットになってしまったこともありました。学んだことは、迷わないように細かく伝えることです。チームメンバーと共通認識を持つためにはもちろんのこと、授業を行っていただく先生方やゲスト講師に私たちの想像していることを汲み取っていただくことは難しいため、先生やゲスト講師にこのように動いてほしい等こんなに細かく?と思うくらいまで、授業案を作成しました。(それでも少し足りなかったかもと思うくらいです)
チャンスがきたら飛び込めるように動き続ける
現状は、なかなか携われていませんが、将来的には、学校現場で中高生に向けたキャリア教育の授業づくりに携わっていきたいと考えています。また、授業だけでなく、一人ひとりと丁寧に向き合い、個々の悩みや迷いにも寄り添えるような支援ができるようになりたいです。まずは、今できることとして自分自身が受けてみたいと思う授業の内容を練習で作ってみるところから始めます。いつかチャンスがきたときに飛び込めるよう、止まらずに動き続けます!
これから学ぶ方へ
キャリア教育という「子ども」たちを中心に集まっている大人たちとのコミュニケーションは、とても刺激的で前向きのエネルギーをいただけます。大変に感じる場面もあるかもしれませんがぜひ楽しんでいただきたいなと思います!

(2025年6月)
子どもたちの未来に向けての一歩!
石井 剛さん(2023年度受講)
自分のキャリアを考える
自分のこれまでのキャリアを振り返ると、学生時代などの進路を考える節目で、実際に働いている方の話を聞く、大人から適切な助言をもらうなどの機会はほぼありませんでした。特定教科への苦手意識からくる文理選択、大学も自身の偏差値範囲内、かつある程度名前を聞いたことのある学校からの選択でした。当時は自分なりに考え、一番と思った選択をしたつもりですが、今振り返ると、どれも消極的かつ狭い人生観からの選択であり、自身の興味・関心や幅広い選択肢からの決断ではなかったと思います。 もしもそういった節目の前に、中長期的にキャリアを考えられる機会があれば、例え苦手な教科でも頑張ることで将来の選択肢を広げられ、後に社会に出ることを見据えての学部選択、偏差値以外での大学選び(アドミッションポリシーや校風等)など、現在と違ったキャリアになった可能性も大いにあると思っています。子どもたちには自分の興味・関心や幅広い選択肢の中から自分なりの決断をして欲しいと考えました。そこで教員免許もない私にも何かできることはないかと調べたところ、キャリア教育コーディネーターという資格に出会いました。
メンバーと協力する活動
授業本番に向けて、学校側と対面で打合せをしたのは2回のみ、それ以外はメンバー間、ゲスト講師と打ち合わせをし、内容を詰め、学校とはメール等でやり取りを行いました。学校初回訪問時は、これまで実施している授業、先生のニーズ、生徒の課題感等を確認。また、ゲスト講師のイメージやOA設備もこの時に確認しました。次の訪問時には、企画した授業プログラムを提案。先生からの要望もあり、事前に検討していたゲスト講師を変更することにもなりました。 メンバーの打ち合わせはオンラインで行い、頻度は1~2週間に1回程度、直前は毎週実施していました。授業のコンセプトを決め、その達成に向けてどんな授業にするかを話し合い、役割を決め、次回打合せまでに自身の課題を仕上げてくるイメージです。ゲスト講師ともオンラインやメール、LINE等を活用し、授業内容を擦り合わせていきました。 授業当日は、私たちは裏方なので、授業がスムーズにいくようサポートしながら、受講する生徒たちの目の輝きを観察していました。授業もやって終わりではなく、学校を通じて生徒たちへアンケートに協力してもらい、狙った通りの授業になっていたか評価もしてもらいます。自分たちの通信簿のようでドキドキしました。
学校の先生は忙しい!
学校の先生が本当に忙しいことを実感しました。実際に2回目の訪問時には学校側でトラブルがあり、60分予定していた打合せを急遽30分で終わらせることになりました。事前準備もあり何とか訪問目的は達成できましたが、あらためて事前の情報共有や当日の説明をシンプルにする大切さを実感するとともに、学校では日々色々なことが起きて、先生がとても忙しいことを肌で感じました。 チームは6名で活動していたのですが、各自これまでの経験が様々なので、でてくるアイディアも全く違い、大変面白かったです。日頃の疲れから打合せ中に意識が飛びそうなことも数回ありましたが・・・(笑)。難しかったのはメンバー間で認識にズレがあったこと。メンバーが一人ずつゲスト講師を担当するのですが、各講師への伝わり方に違いがでてしまい、その結果、教材が違う方向に進んでいることに本番直前で気づいたんですね。本番には間に合いましたが、認識を都度確認する重要性を痛感しました。
地元の活性化につなげたい
現在、直接的な活動はあまりできていませんが、今後やってみたいことは沢山あります。 短期的には、自身の所属する企業内で、CSR、SDGsといった社会貢献をキーワードに、企業価値の向上、採用にも貢献しうることを認識してもらうことで、産業界と学校をつなげる教育プログラムを企画・実行できればと思っています。 また、キャリアコンサルタントという別の専門性を付加し、学校という環境に自ら入ることで、生徒たちとの面談や授業の企画を通じて、キャリアを考える機会を直接つくることも良いなと思っています。 中長期的には、自分の地元(地域)を活性化したいと考えています。私の地元は自然も豊かで、都心へもアクセスし易く、資源に恵まれていながら、うまく活用し切れていないと思っています。そこで、教育を通じて、学校と地域・産業をつなげる教育プログラムを企画・実行し、数多くの教育資源のある魅力的な地域であることを、他の地域に住んでいる方にも知ってもらうことで、地元(地域)の活性化に貢献したいと考えています。
これから学ぶ方へ

学校や地域社会は、皆さんの多様な経験・スキルを求めています。 子どもたちの未来に向けて、まずは一歩を踏み出してみませんか!
(2025年6月)
「キャリア教育×探究」
武口翔吾さん(2014年受講)
今年度のキャリア教育ミニセミナーでは、さまざまなフィールドで活動するキャリア教育コーディネーターに登場していただき、「キャリア教育×〇〇」というテーマで、活動内容についてお聞きしました。第3回のテーマは「キャリア教育×探究」お話しいただいたキャリア教育コーディネーターは、武口翔吾さんです。(2022年7月30日実施キャリア教育ミニセミナーより)
武口翔吾さんについて
一般社団法人ウィルドア共同代表理事
認定キャリア教育コーディネーター
●武口さんがウィルドアとして携わっている企画・活動
〈学校向け〉
・ワンダリングチャレンジ
https://www.wan-challe.jp/
・MAKERS 出張授業
https://makers-u.jp/forschool/
〈社会教育コンテンツ〉
・全国高校生マイプロジェクト
https://myprojects.jp/
・AKRES UNIVERSITY U18
https://u-18.makers-u.jp/
〈中間的企画〉
・willdoor FORUM
https://willdoorforum.studio.site/
「キャリア教育×謎解き」
日景太郎さん(2020年受講)
今年度のキャリア教育ミニセミナーでは、さまざまなフィールドで活動するキャリア教育コーディネーターに登場していただき、「キャリア教育×〇〇」というテーマで、活動内容についてお聞きしました。第2回のテーマは「キャリア教育×謎解き」お話しいただいたキャリア教育コーディネーターは、日景太郎さんです。(2022年7月9日実施キャリア教育ミニセミナーより)
●日景太郎さんについて
認定キャリア教育コーディネーター/エンタメ学習プログラム開発チーム『アソマナクティブ』代表/EdcampTAITO 実行委員/謎解きクリエイター
※運営ブログ
https://asomanactive.com/
※放課後!ようこそ先生!YouTubeチャンネル
https://youtube.com/channel/UC0pn3LNKziF1BJnDGf8WZHA
※Instagram
https://www.instagram.com/kagetaro_asomana/
※Twitter
https://mobile.twitter.com/asomanactive
「キャリア教育×留学事業」
長谷川良介さん(2020年受講)
キャリア教育ミニセミナーでは、さまざまなフィールドで活動するキャリア教育コーディネーターに登場していただき、「キャリア教育×〇〇」というテーマで、活動内容についてお聞きしました。第2回のテーマは「キャリア教育×留学事業」。お話しいただいたキャリア教育コーディネーターは、留学ジャーナルで働く長谷川良介さんです。(2022年6月18日実施キャリア教育ミニセミナーより)
●長谷川良介さんのプロフィール
株式会社留学ジャーナル法人部で、法人(学校や企業)をクライアントに、海外研修プログラムの企画営業を担当。2021年に認定キャリア教育コーディネーターを取得。 ※留学ジャーナルについてはコチラから。 https://www.ryugaku.co.jp/corporate/
キャリア教育初心者がキャリア教育コーディネーター育成研修を受講してどう変わったのか?
すべては「次に」進むためにーーー
山田弘さん (2017年度受講)

キャリア教育コーディネーターの存在を知ったのは2016年の夏頃ですが、まだそのときには他人事でしかなく、まさか自分が育成研修を受講することになるとはまったく思っていませんでした。その後、そんな自分にもキャリア教育の現場体験やキャリア教育コーディネーターの人たちと交流する機会に恵まれたことから、段々とキャリア教育に関わりたいという気持ちが大きくなっていきました。とはいえ、これまで学校教育に関連する事業には全く関わったことがなかったので、とにかく何も知らない・・・知らなさすぎる情けないほどに・・・、このままでは時間ばかりが過ぎていくだけで次に進むことができない。一歩を踏み出すためには集中的に学ぶしかないと思い、キャリア教育を一から学ぶつもりでキャリア教育コーディネーターの育成研修を受講することにしました。
最も重要かつ大変な社会人講師の授業づくり。
実践コースでは、卒業を間近に控えた小学校6年生に向けたキャリア教育の授業を担当しました。私の参加したチームは、自分を含めて2名体制でしたので、ほぼ全ての事にチャレンジする機会に恵まれました。授業でどんな成果を出すために、どんな内容にするのかを考えながら、先生の要望もヒアリングして、何度かチームでの打合せを経てテーマを決めて行きます。テーマに込めた実施の狙いを実現するための授業概要の提案を作成して、先生に提案を行います。先生の合意を得ることが出来たら、そこからは授業を実現するために何をすれば良いのか、そのために何を作る必要があるのかを、チームで打合せしながら役割分担して詳細をつめて作業に落とし込んで行きます。
最も重要で大変だったのは、授業のコアとなる子供たちに働く事の楽しさを伝えてもらう社会人講師の選定とボランティへの協力の依頼。そしてインタビューや打合せを重ねながら、授業の狙いに合うように話していただく内容を調整していく作業でした。着々と準備を進めたあとは、子供たちに狙いが確実に届くように当日の運営をしっかりと回してキャリア教育授業を実施します。最後に、報告会を実施して各チームの参加者やゲストからフィードバックをもらうことで振り返りを行って終了です。
「本番をやりきる」実践コース
ある程度想像していたとはいえ、働きながらの実践コース受講は楽じゃないので覚悟が問われます。受講してみて分かったことは・・・。(ステマじゃないですよ)
●実践コースの正体。
実践コースは講師の話を聞いてロープレして終わる研修ではなく、まさに「本番をやりきる実践」ですから、資格を取ってから「さて、実際にはどうやったらいいんだろう?」ではなく、資格をとったらすぐに実践に移れるように設計されています。そのため、実践コースを受講して本気で取り組むことで、特定のパターンについては拙いながらも何とか一人で回せるぐらいのスキルを身につける事ができます。
●なぜそこまでいけるのか?
実践コースは、授業の企画から実施までを基本的に受講者中心で進めていきますが、講師の方がつかず離れずの距離感でずっと支援をして下さるので、安心して取り組むことができます。そのため、分からないところは聞きながらチームの仲間と最高の体験を積むことができるからです。
●学べること。
キャリア教育の授業のやり方はもちろんですが、授業と授業の準備段階を通して変わるのが、子供たちだけでなく大人も大きく成長することが実感できました。また、受講したことでキャリア教育に関わる人たちと少しだけ共通言語で話せるようになった気もしていますので、この学びと体験は自分にとって大きな成果でした。
次のステップに進むチャレンジに。
育成研修は終わりましたが、知れば知るほどに奥が深く修行が足りないなとも感じるキャリア教育の世界。仕事を続けながらのためすぐにフルタイムでは取り組めませんが、まずはライフワークとしてキャリア教育に関連する事から離れないようにしていくと同時に、リソースの教育資源化についても徐々にチャレンジしていきたいと思っています。育成研修を受講しようか迷っている人、一歩踏み出すことをオススメします!自分のようにキャリア教育初心者にこそ最適なブートキャンプかもしれません。素晴らしい同志との出会いも、自分の成長も、そして子供たちの成長と笑顔も全部コミコミの、次のステップへ進むためのUser Experienceだと思います。
(2018年7月)
ビジネスの視点から考えるキャリア教育の可能性
池田 雄一郎さん (2017年度受講)
私は現在、教育サービス産業の企業(会社員として)に勤めながら、中小企業診断士として活動しています。教育はある意味「聖域」のように感じ、ビジネスを持ち込んではいけないという想いがありました。その中で、会社員としての立場と診断士としての活動の接点にキャリア教育が浮かび上がりました。きっかけは、診断士として支援した地域の商店街が、近隣の高校と連携したいという依頼でした。時間はかかりましたが、試行錯誤の末、両者の希望をかなえ、非常に良い連携につながっています。現在も地域活性のコンサルティングとしてしっかりとビジネスにつながっています。さらにその高校とは、会社員の立場での関係性も構築でき、努めている企業の中でも、新規分野の事業開拓につながっています。こういった背景からその接点である『キャリア教育』をビジネスにしっかりとつなげる方法を学ぶには、このキャリア教育コーディネーターの資格がベストマッチしていると考え、受講に至りました。余談ですが、はじめは「受講料がちょっとお高め?」と感じましたが、実践コースを修了した時には、費用対効果は十二分にあると感じています…
先生のニーズや課題を知ることができた
実践コースでは、学校の要望、子どもたちの状況と成長、そして自分がやりたいことをうまくブレンドして関係者全員が満足する形をどうやって構築するかを学べました。実際には、小学校に社会人講師8名を招いて「大人になることも悪くない」というテーマでグループごとに対話をしながら授業を進めました。今回の企画は、子どもたちの心理的変化を「色」を使って定量的に見ることができないかという視点で考えました。大人になる、仕事をするというイメージ(色)が大人との対話の結果どのように変化したのかを見ることができました。例えば、授業の前では“黒”でもよくないイメージを持っていた子供が、授業後では同じ黒でも“かっこいい”黒に変化したり、まったく違う白という色に変化したケースもありました。我々の予測を良い意味で裏切ってくれました。一方で、お金というイメージから“金”を選んだ子供もいたことから、やはりそうきたか!という想いも感じることができ、大変な想いはしたものの、大きな達成感と充実感を得ることができました。
実践コースの参加者(チーム)が2名しかおらず、招聘する講師の方を探すのに苦労しましたが、少ない人数で進められたため、作業分担がうまくいき、結果学校の先生も子供たちも満足されたと感じています。また、子供たちから講師の方に贈られたお礼のお手紙が形式的でない表現になっていることを見ると、子供たちの成長にもしっかり一役を担えたかなと感じています。特に、子どもたちの参加意欲が、その授業態度にしっかりと現れ、小学生の考えていることや興味があることがどんなものなのかを感じることができたことは非常に大きな経験になりました。さらに、学校の先生がどのようなニーズ(要望)を持っており、課題がどんなところにあるのかということも学べた点は、キャリア教育をどのようにビジネス視点で考えればよいのかという大変良い事例になり勉強にもなりました。(苦労した分、しっかり大きなリターンが得られたと感じています!)
地域資源をキャリア教育につなげ、地域活性化へ。
教育現場でどのようにビジネスを展開すればよいのか、その一旦を学ぶことができました。中小企業診断士の視点から見ると、地域活性を推進するときに、学校と商店街、地域企業などは日本全国どこでも必ず隣接して存在します。地域資源をキャリア教育にうまく関連させ、地域を活性化させるビジネスにつなげていければと考えています。また、キャリア教育は、まさに「生きる力を養う」ということであり、これは日本だけでなく世界で活躍できる人材育成につながると感じています。特に高校生の段階で社会に出るとどのようなチカラや能力、スキルが必要かを学ぶ機会を得られれば、大学進学の方向性や就職に役立つだけでなく、社会人としてスタートした後に成長のスピードが他者と大きく異なると考えます。そのような優秀で活動的、かつ前向きな人材を社会に多く輩出する支援を少しでもできればよいなと感じています。
一般人には見えにくい部分を体系的に学び、ビジネスに活かせる。
キャリア教育コーディネーターの視点は、いくつも存在します。私の場合は、たまたまビジネスという視点から入っていきましたが、子供の成長を見届けることや、生涯学習支援などもあります。教育や学習というある意味一般の方には見えにくい(入りにくい)分野ついて、体系的に知識を整理して学べること、また学校で実際に授業を作り上げることは、このキャリア教育コーディネーターの資格を受講する醍醐味であり、自分の見識を広める良い機会になります。簡単には入りにくい教育(生涯学習も含む)という分野において、学校の先生や関係する人たちと対等に話をするためには、非常に有効な受講コースだと思います。多くの知識を入れることよりも、教育現場の考え方、学習とは、子どもたちへの支援方法など考え方を学ぶ上では唯一の受講コースかと思います。特に実践コースでは実際の授業を組み立てるわけですので、普通は体験できない学びを得ることができます。子供たちの成長を見守りながら支援することに興味が少しでもある方には、おススメできます。
(2018年7月)
できること・できないことを知るために、場数を踏もう。
直江 麻衣子さん (2014年度受講)

私の住んでいる街は、東京五輪が開催される湾岸部だということもあり、我が子の故郷となる街つくりに真剣に取り組みたいという想いを持っていました。また、異なるニーズや文化を持つ、企業と学校・地域をつなげ、教育現場に変化が起きることによって、子どもの成長がどのように変わっていくかにも興味もあり、受講してみることにしました。キャリア教育について、エントリーコースで学んだ概論についてはとても共感をするものの、実際に現場に入った時に、自分に何ができるか、何が大事になるか、または何が難しいかは、場数を踏まないとわからないように感じました。実践コースでは、現場とコネクションを持った現役キャリア教育コーディネーターと一緒に活動できることがわかったので、挑戦してみることにしました。
メンバー内に「本気の想い」が浸透しているか?
取り組んだ活動は、小学6年生が、憧れている仕事人に、自ら手紙を書き、学校に招待し、仕事人から仕事の本当の姿を聞くプログラムでした。礼儀やおもてなしも付随して学び、一連の授業の後には、今後の自分の将来について、思いを深め、できれば行動力に結び付けたい、という内容です。実践コースのメンバーは、手紙を書く授業から見学に入り、仕事人の話を聞いた後に、どのように振り返りの授業をするか、シートや仕事人へのお礼の形などを担当教諭に複数回提案をしました。当日の運営の事前準備や片付けも携わり、振り返り授業にも参加して、生徒たちの変化を定量的、定性的に効果測定もしました。
活動をしながら感じたことは、メンバー内に「本気の想い」がうまく浸透していないと、難題や課題が出た時に乗り越えられず、その結果が、子どもたちにも影響することがある、ということです。それが教育現場の緊張感だったと感じました。キャリア教育プログラムを実行するための成功の鍵は、真剣に目的を練り、それにあった方法をさらに練って、実行するメンバーに同じ想いを共有、浸透することだと感じました。
「子どもたち」や「学校」といっても地域、学年によって多種多様ですから、観察しながら動く、試すという行動力が、“わからない現場をわかっていく”鍵になると感じました。その最初の一歩として、実践コースでのトレーニングは、毎回の活動を振り返りながら、課題の整理や次の方策を練るので、実践経験が積める点で、大事だったと思います。上手くいってもいかなくても、大きな気づきが残ると思いました。
地域のつながりを強める土壌作りを
これから、2020年の東京オリンピック・パラリンピックと学校教育をつなぎ、五輪を教育資源として、役に立てる立場を見つけて、動きまわってみたいと思います。しかし、そのために、地域のつながりを強める土壌が作りは不可欠と実感しています。いろいろな興味や関心を持つ地域の人が、一つの活動に知恵を絞り、労働力を提供してもらうためには、本気を固め、方法を練るのが大前提として不可欠。
新しい街に住んでいるため、教育資源の開拓だけでなく、つながり作りのために、開発が進む街での交通安全から始め、ボランティア活動への啓蒙、ホームページでの必要な情報をタイムリーに提供する広報活動など、地道な活動から始めています。4年後に間に合うかなぁ、と思うこともありますが・・・
(2016年6月)
『まずは自分が変わることから』
河村慎一郎さん(2013年度受講)
自分が知らない言葉に出会いたい。

現在、大学で働いています。19歳や20歳の子たちをよく見るのですが、自分で決められない子たちが増えてきているように感じていました。年々、低年齢化してきているような気も・・・。例えば、「この授業をとるメリットって何ですか?」という質問をしてきたり、「このルールを破ってもいいですか?」という質問があったり・・・ 一方でとても活発に活動している子もいて、その差が広がってきているのでは?という問題意識がありました。それがもし取り返しがつかない状態になるのであれば、いま、自分に何かができるのではないか、と思ってキャリア教育コーディネーターの勉強をはじめました。できるだけ自分が知らない言葉に出会いたかったので、高校生よりも中学生、中学生よりも小学生に出会ってみて、自分が言葉を変えられるのかを試してみたいと考え、小学生を対象とした実践を希望しました。
キラキラした大人に出会えるように
実践コースでは、小学校6年生約60人を対象とした授業のコーディネートを実践しました。ゲスト講師は8名。1回20分×3回で、話を聞いてみたいと思う3人の話を聞くというスタイルにしました。授業のテーマを考える際、最初のチームミーティングで、「キャリア教育とは一体なんなのか?」と「小学生にキャリア教育はどうすれば伝わるのか」を話し合いました。そこでの結論をもとに、学校の先生に提案しました。結果としては、「自分らしく生きるためにどうするか?・・・子ども自身がやりたいという思いを持つこと、自分にもできるという思いを持てること、そこから自分らしく生きる意欲につなげよう」というストーリーにたどりつきました。そのため、ゲスト講師を選ぶ基準としては、「いまキラキラと輝いている人」を条件としました。子どものころにキライだと思っていることも将来につながる可能性があると考えていたので、キラキラした大人が自分のダメなところやキライだったところも語り、「そんな自分だってできたんだよ」と自分の言葉で伝えてくれたら、子どもたちも「自分もできる」と思えるのでは、と考えました。
相手に伝わることばを探す
チームとしての活動は、キックオフが11月中旬、授業の本番は2月半ばでした。チームは僕の他に女性が2人。1人は遠方だったので、予定を合わせるのが大変で、ミーティングでいちばん話題になるのは、「次、いつ集まれる?」でした。そんなこともあり、授業当日の他にメンバー全員が集まったのが4回程度、それに加え、実際に学校におうかがいしたのは授業前に2回なので、授業も含めると7−8回は集まって活動していました。ただし、平日の午後から集まり、そのままメンバーで飲みながら話したこともあるので、一回の打ち合せの時間はかなり長かったと思います。メンバー間での情報共有はメールが中心でした。「私がやります」という積極的なメンバーが多かったので、必要な資料作成は比較的スムーズにできたと思います。僕はチームを代表して学校の先生との連絡をとっていました。先生との連絡は細かいことも含めると合計6回くらいあったのですが、自分が使っている文脈が伝わるのか、本当に大丈夫なのか、をいつもいろいろと考えました。学校の先生は本当に忙しいので、短い言葉で正確に伝えるにはどうしたらいいかを工夫しました。
人を変えたいのであれば、まず自分が変わる。
キャリア教育コーディネーターとして自分が学校に入る場合、先生がいて、ゲスト講師がいて、我々キャリア教育コーディネーターのメンバーがいるのですが、みんな価値観が違います。その中でやっていかないといけない点がいちばん大変です。これは、自分をふりかえることになったというか・・・「ホントにこれでいいんだろうか?」と、つまずいたこともありました。この講座に来るみなさんそうだと思うのですが、僕も「子どもに成長してほしい」とか「来てくれるゲスト講師にもプラスになるものを得て帰ってほしい」とか、なにかしら「人を変えたい」と思っていました。でも、そう思っているのであれば、まずは自分が変わらないといけないのでは?と気づきました。自分がこれまで積み上げてきた文脈を通そうとするのではなくて、いちど「本当だろうか?」「なぜ自分を変えないんだ?」と問いかけ、自分のやり方を見直すことが必要でした。しかしこれはもしかすると、人によっては、いちばんツライ作業になるかもしれません。経験があればあるほど、これは残酷なことだったりするので、直面したときにどれだけがんばれるか、というのは大事かなと思います。では自分が変われたのかというと、実はそんなことはなくて・・・。普段の自分であれば、話を聞いて必要なときだけプッシュをするというタイプでしたが、今回は、講師の方から「リーダーとして少しひっぱってみては」と言われて・・・やってみて失敗した部分も含めて、少しは変われたのかなと思います。
自分自身が広い視野を持つことから。
授業で出会った子どもたちはみんな素直で元気で、でも大人と出会うと、目が輝くというか・・・子どものうちにいろんな価値観に出会うことって大事なんだなと思いました。実践コースの最後の活動のふりかえりの際、僕は学んだこととして「みんなを巻き込む」をあげました。担任の先生がいて、校長先生がいて、ゲスト講師がいて、みんなそれぞれ想いが違うのですが、それでも「一緒にやろうよ!」と言えたのは、「自分が楽しもう!」と思えたからかもしれません。いろんな価値観の人がいて大変だけど、そこで苦労をするのもいいのではないか、人に影響を与えたいのであれば、自分が楽しんで変わろう・・・と。 また、この講座を受けてみてよくわかったのは、学校の先生相手に「教育ってこうだよね」なんて偉そうなことは言えない、ということです。だったらもっと現場を見て、いろんな人に出会って、自分自身が広い視野を持っていないと、メッセージなんて持てないんじゃないかなというのが、ここでいちばん学んだことかなと思います。
(2014年10月11日 実践コース説明会より)
『学びの環境を変えるために』
沼田翔二朗さん(2013年度受講)

学びの環境を変えるために
受講動機のいちばんは、「学びの環境を変えよう」ということでした。普段は群馬県で活動しています。群馬は不登校・ひきこもりの支援はあるんですが、学校教育と連動したキャリア教育の取り組みはまだ少なかったので、群馬でそういう場を作りたいと考えていました。いまは休学中なのですが、もともとは大学院で「能動的学習」という学習方法を研究していました。PBL(Project Based Learning)など、大学教育の中で大学生と一緒に活動してきたのですが、高校でも取り組みをしてみたいと考えていました。しかし、学ぶ環境がなかったので、環境を変えようというのが受講のきっかけです。実践コースの受講も「これしかない」と思っていました。群馬県にモデルがないのでモデルを作りたい。そのためにはお金を稼ぐ必要があって、そのためには授業の質が問われるので、自分を磨く必要がある・・・いろんな意味で人生をかけて受講していた感じです。
既存プログラムの「向上」フェイズ
実践コースで取り組んだ活動は、高校1年生180名に対して、12月から4月までのカリキュラムでした。現一年生が新一年生に対して自分の高校の魅力を伝える45分間の交流企画を作るというもの。交流企画のために現一年生は1年間をふりかえり、何を新一年生に伝えるのかを考えるという、全部で8回の授業です。この授業は3年前からやっていたので、プログラムのだいたいの流れはあり、フェイズとしては「向上の時期」でした。そこで担当の先生からは「生徒同士の議論が深まるようにしたい」「生徒同士で進行できる状態にしたい」というニーズが出てきていました。なので、実際に工夫したこととしては、「進路係」という進行役を作ったことと、議論を深めるためにワークショップ形式にしたり・・・という提案をしていきました。しかし、できなかったこともたくさんありました。いちばんの失敗は、外部人材です。カリキュラムの中には大学生に協力してもらう部分があったのですが、お願いする大学生の連絡をしなさすぎて、大学生に叱られたことが失敗でした。大学生も忙しいのですが、社会人よりは時間があるだろうという勝手な甘えもあって・・・
正直ツラかったチームでの活動
チームメンバーは、僕の他に長野在住の方でした。僕は24歳だったのですが、相方は50歳代。身長の差もあったので、先生や生徒には「凸凹コンビ」と呼ばれて覚えてもらうことができました。しかし、群馬と長野、また講師が東京だったので、ミーティングをするには予定が合わなかったんです。全8回の授業は全員参加ですが、10回以上あったミーティングは、メールでやりとりしたり、スカイプでやりとりしたり、ということをしていました。正直・・・つらかったです。とくにWEB上でのやり取りの際は、コミュニケーションエラーが発生したこともありました・・・。価値観の違いもあったのですが、授業とは関係ない話もたくさんして、相方とは良い関係を作ることができたと思います。
また、講師が「人に妥協しない」精神の方で、ものすごくクオリティの追求をするんです。これはおそらく我々の甘えなのですが、「このくらいでいいだろう」とか「このワークシートで流れが組めるだろう」で提出すると、すべてに赤が入るような状態でした。僕と相方の二人で「・・・途方にくれましたねぇ・・・」なんて、ため息をつくこともありました。でも甘えていた部分を指摘されたことで成長できたと感じました。
高校生が変わる瞬間に立ち会えた
いちばんやりがいを感じたのは、高校生の変化の瞬間に立ち会うことができたことです。現場に入ると、自分が思い描いていた高校生像と、本当にリアルな高校生像に、ギャップがあったりします。どちらかというと性善説で生きていたので、高校生はきっと素直だから言ったらやってくれるだろうと思って学校に行ったら、全くそうではなくて。でもそれは生徒に意欲がないというわけではなくで、こちら側が生徒の意欲感心を寄せられていないということなので、いかに興味関心を持てる環境を作れるか、ということなんです。また、「議論を深める」という先生からのニーズがあったのですが、授業の中で実際に議論が深まっていく様子や、高校生が変わっていく瞬間が見れたというのは、凄くやりがいを感じたし、自分としてもやってよかったという実感を持てました。自分もこういう仕事をどんどんしたいと思えました。
「これから」に活かすべきこととは?
いくつか学んだことをあげてみます。まずは、生徒が変わる瞬間を見逃さないこと。生徒自身が勇気を持って質問したり働きかけたりすることってあるんですが、いまの大学生とかも、自分も評価してもらいたいという思いがある。大人にとっては何気ないひとことでも、その子にとっては勇気を持って起こした行動だったりするので、それを見逃さずに声をかけられることは大事だなと思いました。次に「伝える」と「伝わる」は違うということ。自分がやってほしいことがあっても、伝えることと、それをやれる状態になることは全く違うのだな、と。また、「“誰のためか”は当然で“誰の視点か”」。子どものため、先生のため、関わる企業のため、は仕事をする上で当たり前のことだと思うのですが、もう一歩先にある「誰の視点なのか」が大事だなと思いました。例えばワークシートなど、大人の目線では使えるのですが、よく講師に指摘されたのは「これでは高校生ができないよ」ということでした。なので、授業の中でもワークシートを使っている様子をしっかり見て、どこでつまずくのかを観察したり、授業後に高校生と話をして反応を確認したり・・・ということをしていました。「自分が高校生だったときにわかっただろうか」もいつも気にするようになりました。また、先生向けの授業進行案を作るときは「先生が進行しやすいように」作る必要があるということも意識するようになりました。 いま、群馬で活動を展開していますが、おかげさまで、ある高校でコーディネーターとして活動させていただいています。そこをしっかりとやっていきながら、僕が重要だなと思っているのは、「自ら答えを作りだしていくこと」なので、高校の教育現場で先生と協働しながら、これからの高校生の学びに貢献したいと思っています。
(2014年10月11日 実践コース説明会より)